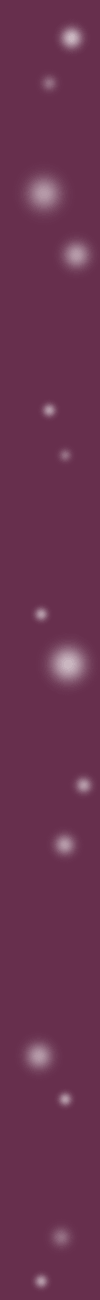今
速水が薄暗い玄関を開けると、リビングのドアから明かりがもれているのが見えた。
──またか。
方頬に苦笑を浮かべながら、速水は後ろ手でドアを閉めた。下駄箱の上に鍵を置くと靴を脱ぎ、短い廊下を大股で歩く。
そっと、細く開いているドアを引いた。
速水が思った通り、安積がソファに背中を預け、静かに眠っていた。
かろうじてテレビの電源は落ちているが、リビングの明かりは煌々と灯っている。テーブルには、氷の溶けたウイスキーグラスがひとつ置かれていた。
合鍵を使うのにようやく慣れた安積だったが、無断で主人のいないベッドを借りるのは、まだ気が引けるらしい。
何度注意しても、安積は速水のいない夜、リビングのソファで夜を明かすのだ。
呼吸音さえほとんど感じさせないほど、安積は深く眠っていた。
ずいぶん、疲れた顔してるな。
肩に触れようとした手をとめ、速水は安積の顔を見つめた。
うすい瞼に、青白い血管が透けてみえる。その下の濃いクマが、疲労の強さを物語っていた。後ろへ流している髪もやや乱れ、前髪が額におちている。
──まっすぐ家へ帰れば、もう少しまともに休めただろうに。
なにか掛けるものを持ってくるか、と思いながら、速水は安積に見入ったまま、動けずにいた。
何週間も二人きりの時間がとれないとき、安積は連絡もなく、速水のマンションへやってくるようになった。たいていは速水が出迎えるが、こうして合鍵を使い、待っている時もある。速水はそれがうれしい半面、安積に余計な負担をかけている気がしていた。
『後悔はしない』
安積を腕に抱いた時、速水は自分に誓った。
──後悔も、させない。
何度同じ場面を繰り返したって、俺はこいつを抱きしめるだろう。
だが、安積の疲れた顔を見ていると、心に迷いが生じるのも確かだった。
こいつには、もっと安らげる場所が必要なんじゃないか。
俺は、安積と共に戦うことができる。戦友(同僚)として、ずっと同じ道を歩いていける。
だが、ほんとうに、安らげる場所は──
少し寂しそうなまなざしの女性と、はつらつとした少女の面影が、速水の脳裏をよぎった。
速水は、安積に覆いかぶさるようにしていた身を引くと、硬い表情のまま立ち上った。
その時、立ち上った速水の気配を感じたのか、安積がうっすらと目を開けた。
ぼんやりと目の前のウイスキーグラスをみつめ、それから速水のジーンズと靴下に気づき、ゆっくり、ゆっくりと長い間かかって、速水の顔を見上げる。
眩しそうに目を数回しばたくと、ふっと、口元をゆるめ、安積が言った。
「おかえり。……おつかれ様」
ほほえみに誘われるように、速水は安積へキスをした。
「……なにか、あったのか?」
いつもより少しだけためらうような口付けに、安積はなにか感じたようだ。
そっと速水の肩に手を伸ばし、二、三度なだめるように、軽く撫でた。
「いや。ひさびさのキスに、緊張してな」
速水は真っ直ぐに見つめてくる視線を軽口でかわすと、
安積の手を取ると指先へ唇をよせた。
その手を握りしめたまま、安積のかすかに濡れた唇に
再びくちづけを落とした。
今、安積がここにいる。
それが、俺に対する、安積の答えだ。
深く唇を重ねながら、速水はひそかに、こう自分に言い聞かせた。
──それなら、もうなにも、迷うことはない。
END